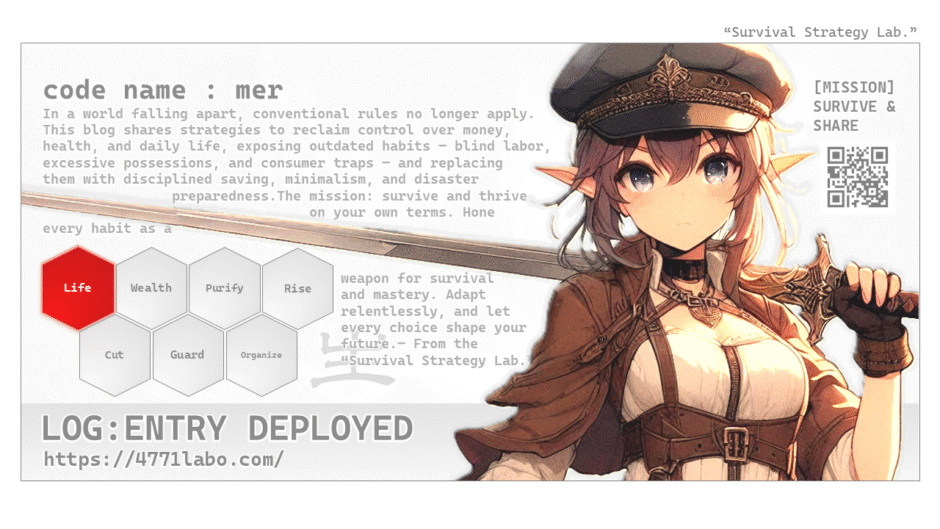> MEMORY CHECK ........ OK
> STORAGE MOUNT ....... OK
> USER: VISITOR
> ACCESS LEVEL: READ
> LOADING ENTRY...
> TIMESTAMP: 2026-01-28 23:28:35
> STATUS: READING
みなさんこんにちは、マーです。
節約上級編の5つ目は労働を減らすことです。これだけ聞くと節約と労働がなぜ結びつくのか疑問に感じられることでしょう。
労働が消費を加速させる?
労働を減らすと書いた理由は2つあります。一つは労働が必要以上に消費の呼び水となること、もう一つは定期収入があることにより緊張感が薄れることです。

立派な収入源なのに減らせってこと?
私も含め労働したことのある多くの人は、仕事でストレスを抱えたことがある人かと思います。
適度のストレスは老け込まないためには大切ですが、日本国内の多くの労働環境は少ない資源でやりくりしていたり、経営者の都合ばかり優先する企業文化だったり、それに対して報酬が過小評価されていたりなどと労働者側にとってマイナス要素を多くはらんでいる傾向があります。
カビ臭い法律は労働環境を良くしない
そもそも現代の労働基準法(労基法)は工場等における単純労働、肉体労働、集約労働における労働者を想定して作られた旧態依然とした法律で、1日8時間・週40時間や長時間残業の温床となる「36協定(サブロク協定、労働基準法第36条)」を謳っていたりします。

工場勤務の前提なんだ。
仮に罰則を犯しても最も重いもので「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」というぬるいものです。
そんな労基法ですら経営者の中には「労基法を遵守していたら倒産してしまう」と宣う人もいますが、そうした会社は従業員を犠牲にしてやっと成り立っている会社なのでつぶれてくれたほうが社会的に善であります。

法施行当時よりインフレしているから。20万円って今だと初任給レベルだよ。
これがすべてではないにせよ、こうした環境がまかり通っているのは社会風土や価値観などの影響もあるでしょうが、古臭い法律が国内の労働環境を悪くしている元凶の一因でしょう。

労基法成立は1947年。78年も前のルールでは時代遅れもいいところだよ。
少し話がそれました。労働は生きていくためにお金を稼ぐ一手段ですが、そのためにストレスを抱えて心身を壊して多額の医療費をかけたり、また心身を壊さないまでもストレスから浪費してみたり、本当は必要のない時短家電や過剰な自己投資に使ってしまうのはあまり意味のある事とは思えません。
満額きっちり回収できる前提って、カイジの「鉄骨渡り」みたいなもの
また毎月稼げるという慢心から今月くらいは使ってしまおうと緊張感が薄れやすいことも、消費を加速させやすい一因です。

次の給料日さえくれればなんとかなるもんね。
前述の労働基準法では毎月一定期日に通貨で直接支払われることを謳っていますが、倒産寸前とか未だに現金手渡しとかの理由で給与支払い日に受け取れないということはあるものです。
さらに年に数回賞与が支給されるケースであっても、今年は業績不振だとなれば減額、ないしゼロということも十分にあり得ます。
「働いているから使ってもいい」を免罪符にしていない?
つまり未払いの報酬をあてにして消費してしまいがちなのです。
もちろん修行僧のように一切使うなという話ではありませんが、稼いでは使うという自転車操業のような生活ができてしまうから注意しなければいけません。

給料日まで我慢すれば何とかなる、ってのは落とし穴だったのか。
そのためにあえて労働を捨てましょうと書きました。もう少し付け加えて言うなれば、「消費を正当化させるために労働を持ち出す言い訳」を捨てよう、です。
労働を消費理由につなげない
ではどのように労働習慣を捨てればよいのでしょうか。
無職になるという考え方もありますが、なんらかのFIREを達成していなければいずれ労働者に逆戻りです。
ですから現実的な対策としては長時間労働や労働によるストレスをなくす環境に移ること、あるいは今まで正当化していた消費活動を大幅に削減することです。

移るか減らすか。どっちも大変そう。
これを実行するのは大変です。なぜならそもそもお金を持っていない人ならば必死に取り組むだけの動機がありますが、この節約が有効なのはなまじ中途半端にお金を持っている人で、いま生活できているだけにかえって必死に取り組もうと考えないのです。
メンバーシップ型に常態化する長時間労働、おまけに法律も古い。これで世界に立ち向かうとかw
それならば仕事を効率化して定時で上がればよいと考える人もいるでしょう。
ですが仕事を効率化したりスピードを上げたりしてもあまり効果はありません。なぜなら仕事は無限にあり早く終わればすぐに次の仕事が降りかかってくるからです。
本来他の同僚がやるべきだった仕事を割り当てられたりして、結局定時に終わらないのです。

定時なのに帰りにくい会社もあるからたちが悪い。
海外では専門職が決められた仕事を遂行する「ジョブ型」と呼ばれる雇用形態が主流ですが、こと日本では職場内の仕事をみんなで分け合う「メンバーシップ型」と呼ばれる雇用形態がいまだに幅を利かせており、自分だけお先に帰ることを良しとしない風潮が厳然としてあります。
結局、これが日本で生産性の上がらない要因の一つで、それが私たちのストレス消費にもつながっているのだろうと考えられます。

「お前だけ先に帰るのか?」みたいな圧をかけてくる社畜がいるからクッソ面倒なんだよ~
今にこだわっても変わらないなら環境を変えたほうが早い
働いて稼ぐことで思考停止してしまい自分の癒しや今より効率的に稼ぐためと理由をつけて必要以上に経費を使ってしまう。
これでは何のために労働しているかわかりません。とはいえ経営者でもない個々の労働者レベルで労働環境を改善させることは非常に難しく、だからこそ環境そのものを変えましょう。
次回の節約上級編は横並び主義を捨てるについて考えてみたいと思います。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。

旧態依然の法律と制度から逃げよ
> STATUS: OBSERVED
> SYSTEM WAITING
 生きぬく!研究所
生きぬく!研究所